1/22(月) 18:03 現代ビジネス
https://news.yahoo.co.jp/articles/058462d7d06f82868cf56c8b0e8f71a470587e22
写真/講談社

世代もジャンルも超えて愛されたロックの伝道者、忌野清志郎。亡くなって15年経った今なお、愛される理由とは何か――。
■「RCサクセション」熱狂の時代
清志郎率いる「RCサクセション」は1970(昭和45)年、『宝くじは買わない』でデビューを果たす。だが、フォーク・トリオだった初期のセールスは芳しくなかった。
転機となったのは’78年。ドラムスに加え、後に盟友となる、仲井戸”チャボ”麗市を迎え入れ、5人編成のロックバンドに変貌を遂げると、一気にスターダムへとのし上がっていく。
「愛しあってるか~い!」
清志郎のシャウトに、チャボのギターが妖しく絡む。その姿に若者たちは熱狂した。
著書に『忌野清志郎が聴こえる』がある、作家の神山典士氏も、伝説を間近に見たひとりだ。
「’80年、当時大学生だった私は、伝説的な久保講堂のライヴを収録したアルバム『RHAPSODY』を夢中で聴き続け、全曲を覚え、コンサートに出かけました。会場にはパイプ椅子をなぎ倒しながら、ステージ前に殺到するファンたち。片や私は客席後方で踊りまくっていました」
愚直なまでに愛を、哀しみを、社会への問いを音楽に昇華させていく。一曲の歌詞を書くために大学ノート3冊を費やすほど、たったワンフレーズにもこだわったという清志郎。数多くの共作を生み出してきたミュージシャン、三宅伸治はこう証言する。
「ボスは何か思いつくと、すぐに僕たちにFAXを送ってくるんです。その発想力がすごかった。身の回りの喜怒哀楽を上手く歌詞に落とし込んでいて、そこに多くの人は魅せられたんだと思います」
■シャイな心の内に秘めた、音楽への熱量
「ド派手な衣装や過激なパフォーマンスとは反対に、素顔は物静かでシャイな方でした」
そう話すのは、’80年代に「RCサクセション」のマネージャー兼衣装係を担当した片岡たまき氏だ。
バックヤードの「静」とステージの「動」。この2つが共存する背景には、清志郎の生い立ちが関係している。
’51年に生まれた清志郎、本名・栗原清志は、3歳で実母を亡くし、母の姉夫婦の元で暮らす。複雑な家庭環境での淋しさを紛らわすため、小中学校では絵を描くことに没頭。寡黙な少年時代を過ごしたという。
ターニングポイントとなったのは中3の時。フォークギターを手に入れた清志郎は海外の音楽にのめり込んでいった。
〈いつかオーティス・レディング(米国のR&Bシンガー)のようになりたい〉
そんな熱い夢を抱いて、中学校の同級生とRCサクセションの前身、「ザ・クローバー」を結成。高校に上がると、同バンドは「RCサクセション」へと名を変え、高校卒業と同時にデビューを果たしたのだ。
「ライブ前、清志郎さんは楽屋でカセットレコーダーから流れるロックやソウルを聴きながら、髪を立て、独特のメイクを施すことでスイッチが入っていく。その恰好も言動もすべて、音楽への熱量を表すものだったと思います」(片岡氏)
(※中略)
’09年、清志郎の葬儀で弔辞を読んだ俳優・竹中直人はこう振り返る。
「清志郎は優しい人だった。よくぼくに電話をくれた。『もしもし忌野ですが』って。『竹中、いま竹中主演のドラマ見てるぞ。出番ないか? 』『え? 清志郎さん、出てくれるんですか? 』『うん出たいんだよね』『でも清志郎さん、そのドラマ視聴率一桁なんです……』『え? あっ そうなんだ』とうろたえつつも『竹中~! 』っていつもぼくの存在を認めてくれました」
(※以下略、全文は引用元サイトをご覧ください。)
引用元: ・【音楽】亡くなって15年経った今なお「忌野清志郎」の“歌と人間性”が突き刺さる理由…竹中直人が明かす「素顔」 [湛然★]
野音で見たな
あれはいつだったか
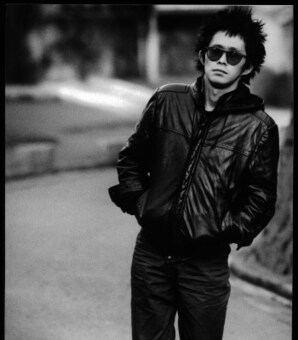
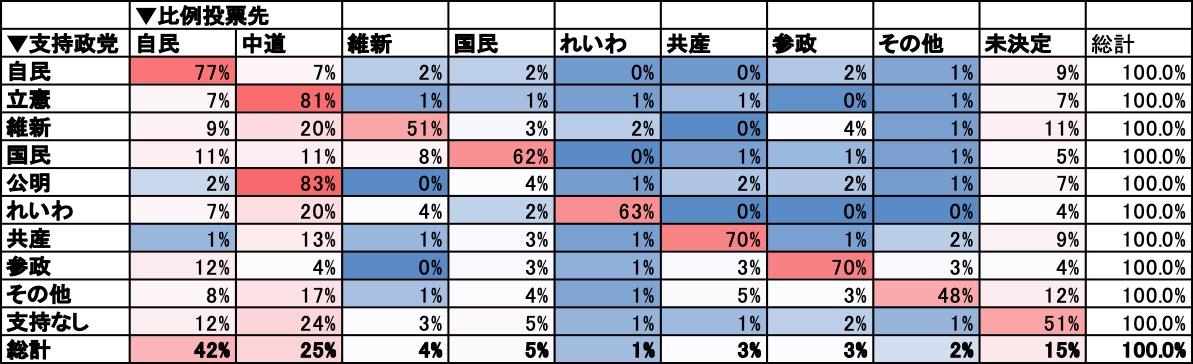









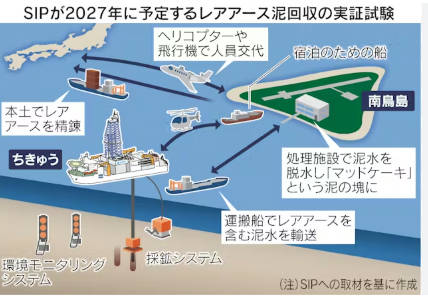

コメント